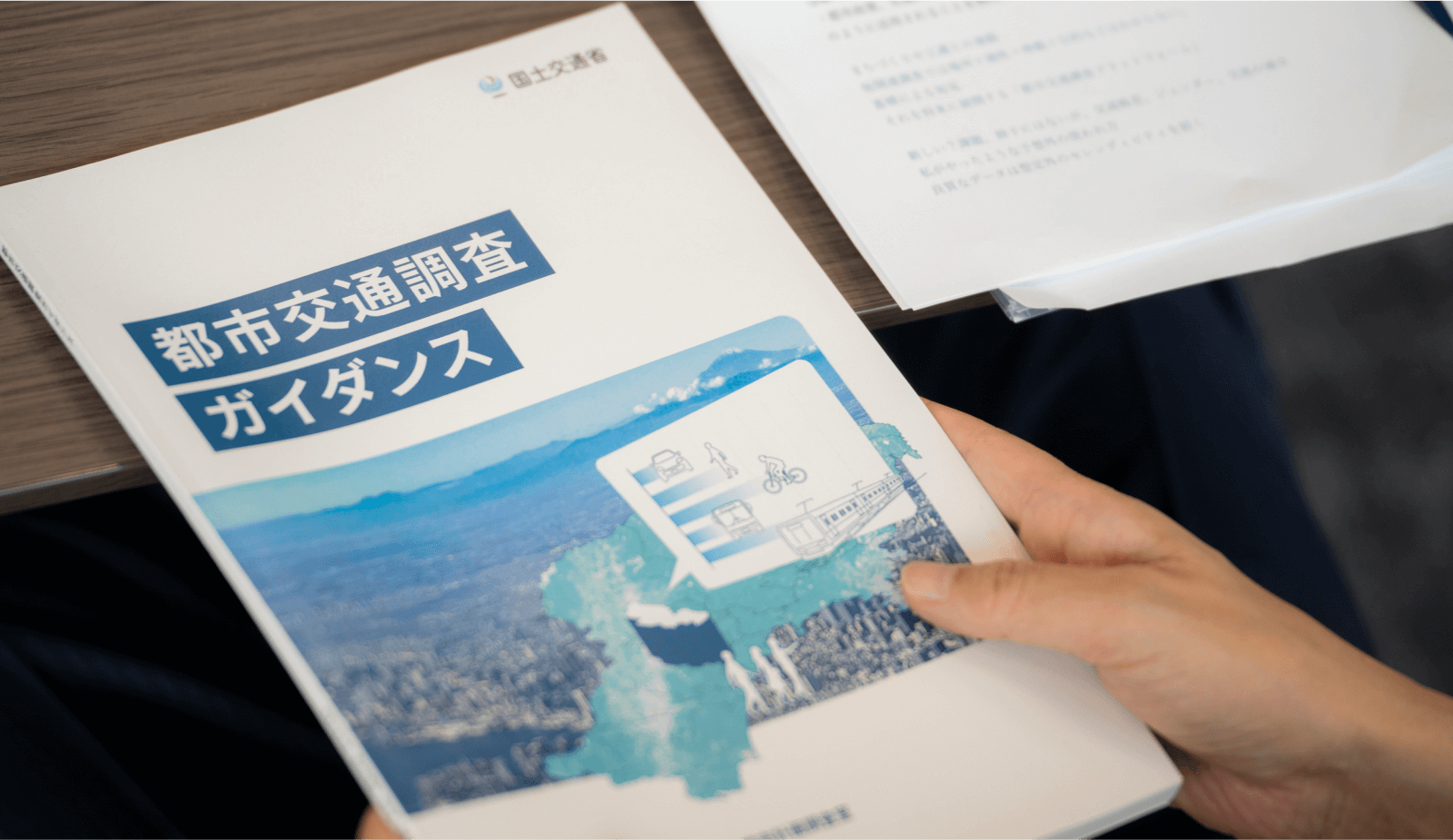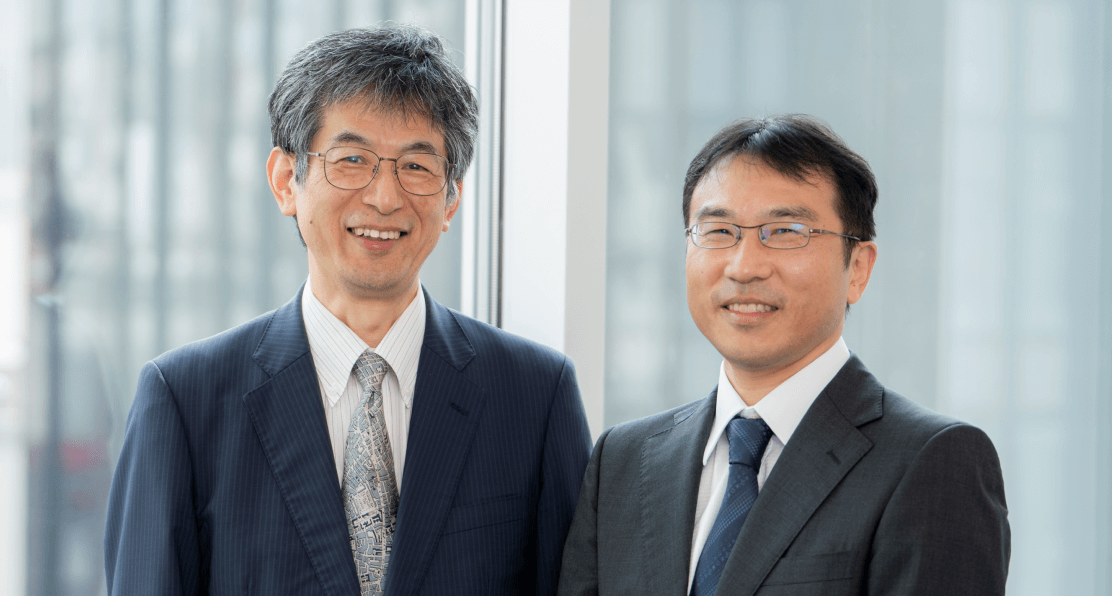- ホーム
- 活用事例・調査事例・Tips
- 特別インタビュー後編
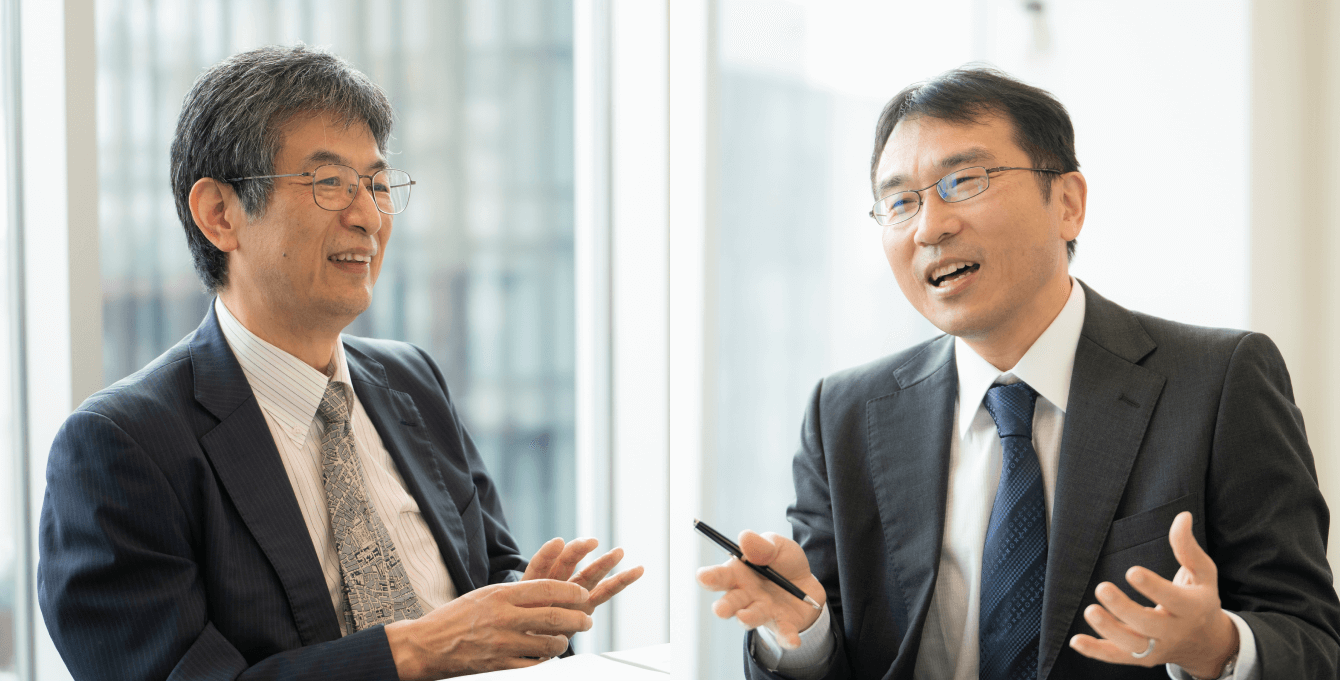
自治体のまちづくりに「都市交通調査ガイダンス」を
どう活かすか
後編:多様化するまちづくりを実現させるために
プロフィール
谷口 守
筑波大学
システム情報系社会工学域 教授

京都大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得退学。工学博士。京都大学助手、カリフォルニア州立大学バークレイ校客員研究員、岡山大学環境理工学部教授などを経て2009年より現職。専門は、都市・地域計画、交通計画、環境計画。全国都市交通特性調査検討会委員長、東京都市圏総合都市交通体系調査技術検討会委員長、新たな都市交通調査体系のあり方に関する検討会座長など、都市交通調査に関わる多くの委員を歴任。
田中 成興
国土交通省都市局都市計画課
都市計画調査室長
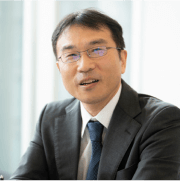
1999年、建設省に入省。まちづくりに関する分野を中心に従事し、草津市役所、首都高速道路(株)、JICA長期専門家(ミャンマー建設省)などでの幅広い業務も経験。まちづくり推進課国際競争力強化推進官、市街地整備課拠点整備事業推進官、街路交通施設課街路事業調整官などを経て、2024年7月より現職。
新しいガイダンスを策定する上で検討会の委員たちが目指したものとは? 検討会の座長を務めた筑波大学・谷口守教授は、「すでにまちづくりの教科書がない時代に入っている」と言う。大きく変化する都市交通調査のあり方をリードするガイダンスの内容を読み解く。
「都市交通調査ガイダンス」が見据えたもの
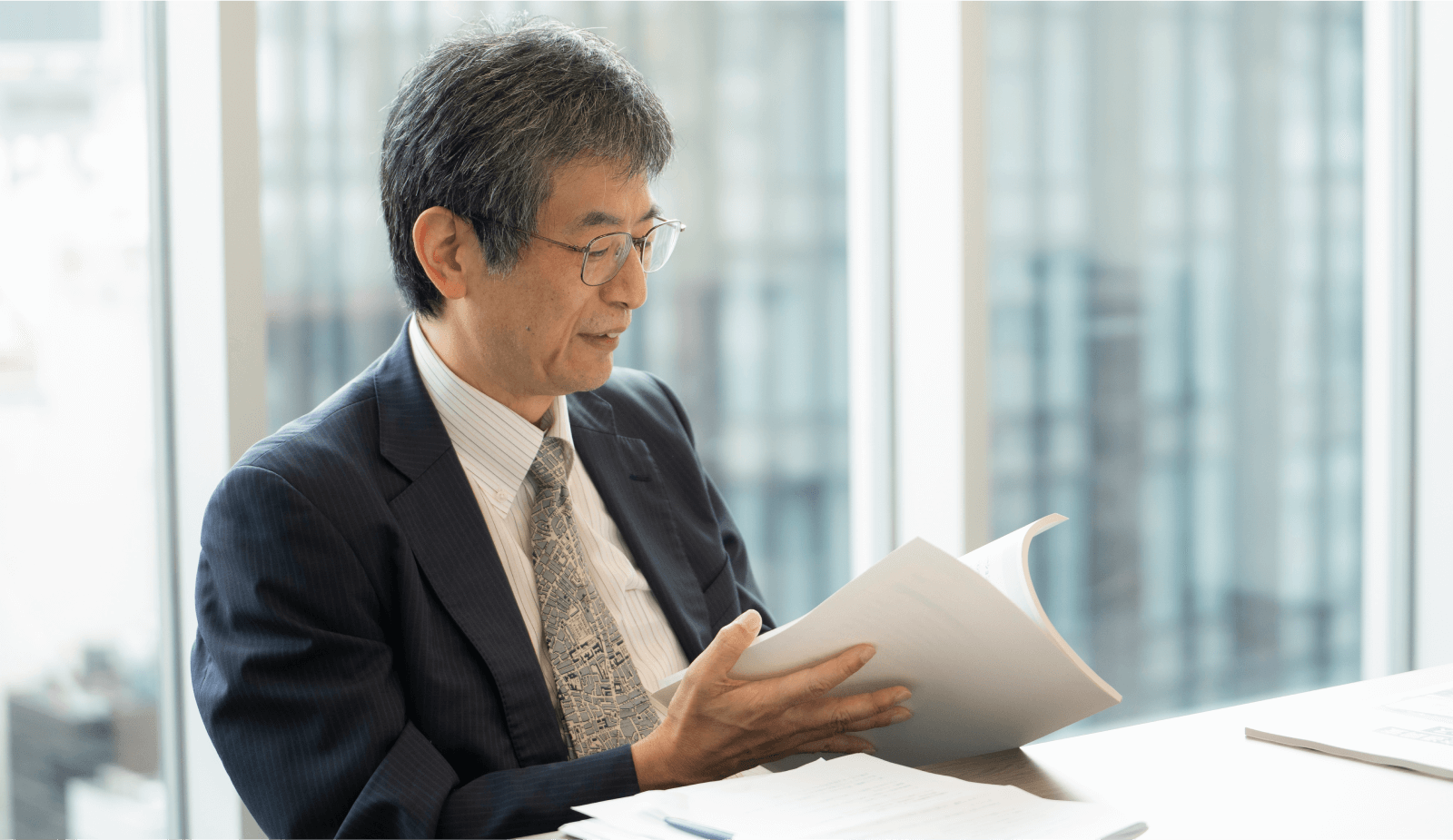
谷口先生:
我々が学生の時には、右肩上がりで交通量が増えている時代だったので、「四段階推定法」という交通需要予測を覚えておけばいいという定番がありました。しかし、今の時代は、地域の特徴も課題も多様化しています。それぞれの場所ごとに都市交通調査の内容を考えないといけない。そこがかつてとは大きく違うところで、「いよいよ教科書のない時代に突入してきた」と感じています。
ですから、「地域ごとに、それぞれの場所で考えてください」というメッセージもすごく大事だと思う。まちづくりの指針となるガイダンスは、誰が読んでも理解できる簡単なものでなければいけませんが、それを見て、この通りにやったら全部できるというものでもありません。場所によって課題も違うので、その課題に応じてオプション的に調査内容を加えることも考えないとならないわけです。今回の新しいガイダンスを作成する際には、徹頭徹尾そこを注意して考えていました。
都市交通調査に関することは、素人がすぐにできることではありません。都市交通調査には多様な経験や蓄積があり、それをどう引き継いでいくかということが大切です。
その一方で、デジタル技術など、新しいものも上手く取り込むことも重要ですので、その両方をどういうふうに入れ込むのかが、大きなポイントだったと思います。
もう一点、「これから交通計画を勉強しよう」と思っている学部生が手に取ってパラパラと見て、「これ面白いな」というふうになればいいなと考えていました。実際のガイダンスはインターネットからダウンロードする仕様になっていますが、モノとしていろいろなところにおいていただけるようになるといいなというのが個人的な希望です。
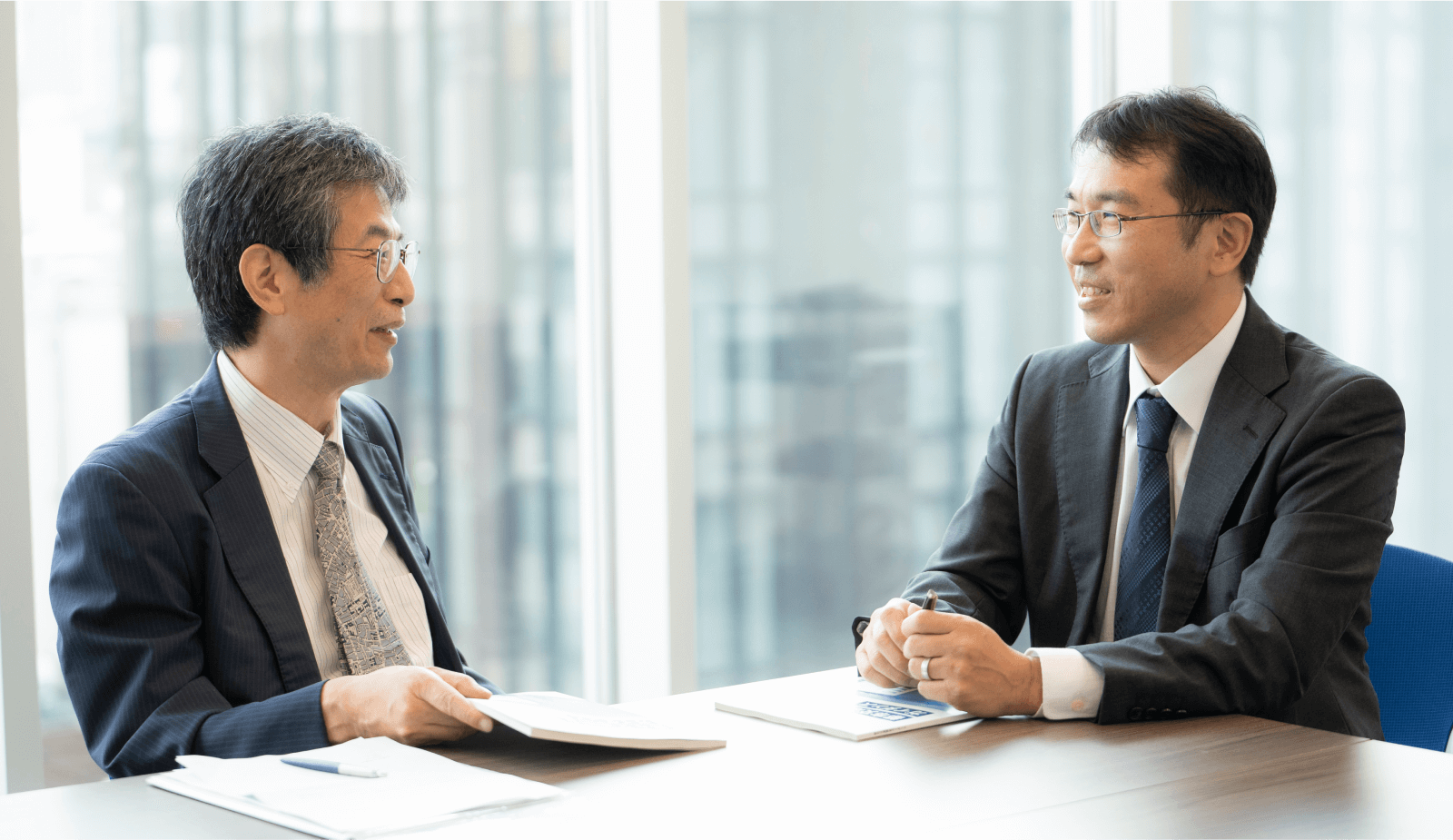
田中室長:
検討会では、テキストの表現に至るまで本当に細かいところまで助言をいただいて今回の「都市交通調査ガイダンス」ができあがりました。また、調査手法に関しても、活動の変化に対応するためのさまざまなアイデアも提示していただきました。
例えば、基本的には代表的な1日を調査するものですが、現在、テレワークがずいぶん浸透しました。当然、テレワークは毎日ではないという状況も考えられます。テレワークを実施している日とそうでない日では人の活動もまったく違うものになるので、それらを補足できるようにしたほうが良いのではないかということなどなど。まだ調査手法が確立されていない中でも実情に即してコメントをいただき、できるだけガイダンスの中に入れていこうと検討されたこともありがたかったです。
谷口先生:
実は、今回の改訂に当たっては、検討した内容があまりにも幅広かったので、当初は「本当にできあがるのかな」と不安に感じていました。テレワークの話をどういれるのか、モニター対応で調査したら上手くいくのか、調査のやり方自体を抜本的に変えた方がいいんじゃないのか。研究者としては勉強になりましたが、本当に検討事項が多かった。
あと、都市交通調査を過去に担当したコンサルタントが後ろに控えてくださったことで、非常に厚みのある議論ができたと思います。そのぶん、「最後はどれだけ分厚いガイダンスになるんだろう」と懸念していましたが、よくこれだけスリムになったなと。
新しいガイダンスのポイント
田中室長:
今回の「都市交通調査ガイダンス」の最大のポイントは、従来目的としていた都市交通マスタープランの策定やそれに基づく事業を検討するためだけでなく、いろいろな幅広い施策への適用を想定し、改定をしているということです。
もちろん、都市交通マスタープランの策定も大切ですが、人口減少時代になり、「今あるインフラをどう使うか」「その限られた財源でどうしていくのか」という話になった時に、施策のあり方がマネジメント重視へと変わってきています。
世の中が成熟してニーズが多様化している中では、1つの課題に対して1つの解決策だけでは対応できません。多様な課題に対して総力戦で対応していくことが大切です。そのような中では都市交通調査も幅広い分野、施策に対して活用していくことが必要になってくるはずです。
質の高いデータが生み出す価値
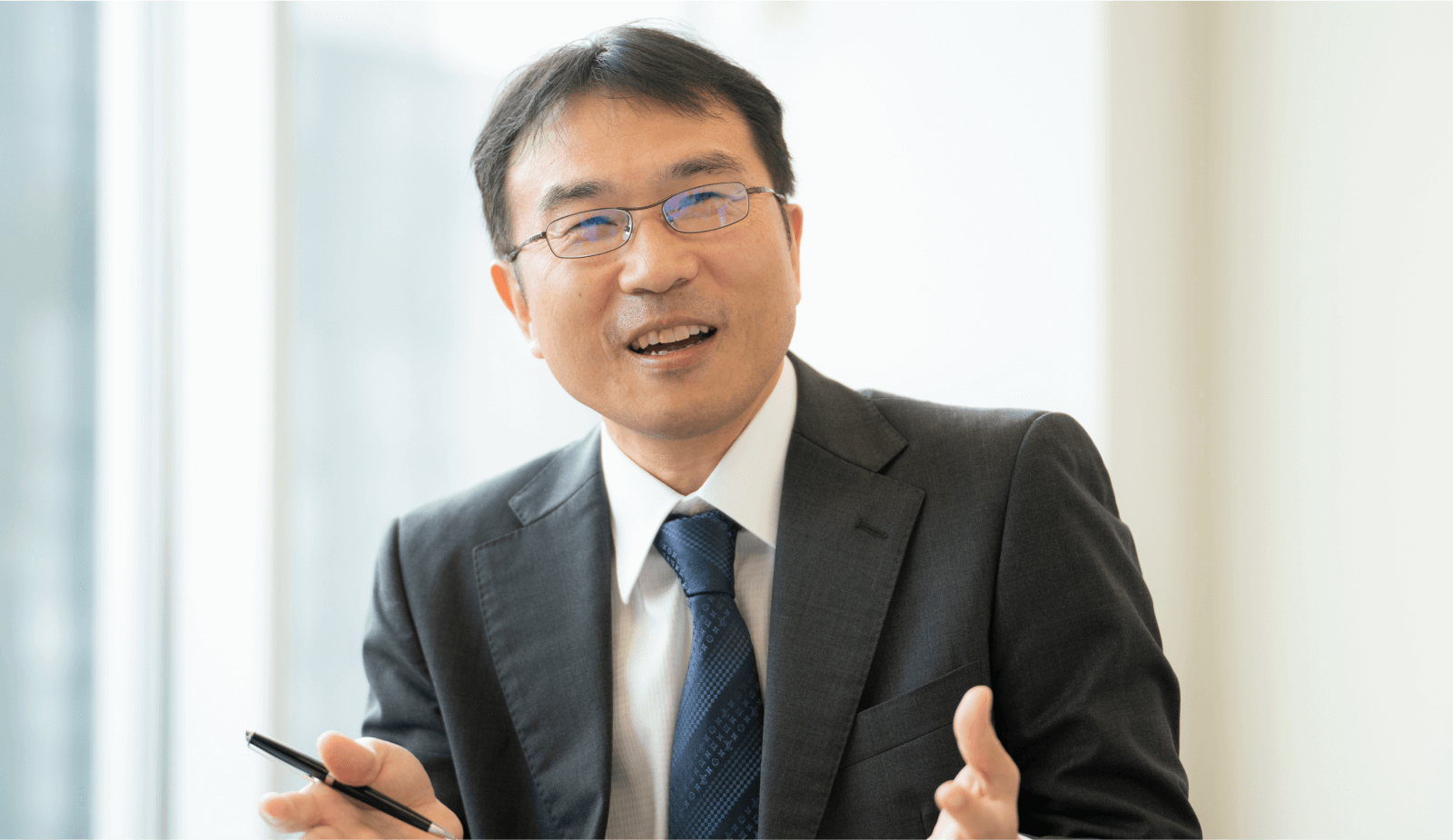
田中室長:
現在、国では、都市交通データや都市計画情報などさまざまなデータのオープン化を進めていますが、ぜひ民間の方も含めて数多く使っていただき、色々な使われ方をすることで多くの分野でイノベーションに結び付くのではないかと思っています。
谷口先生:
質の高いデータであれば、オープンにしておくことで、勝手に使われていくものです。私も都市計画の研究者として、これまでずいぶんとパーソントリップ調査(以下、PT調査)の上質なデータを使わせてもらってきました。
「都市」と「交通」はとても関係性が強いものですが、私が研究者になった頃は両者をつなぐ研究をしている人がほとんどいなかったんです。でも、PT調査の結果を見れば、性格が異なるいろいろなまちの交通データが分かるので、研究対象として非常に分かりやすかった。「なるほど。これとこれを組合わせたらこんなことができるんだ」と。
ですから、多くの研究者やビジネスパーソンになるべく勝手な使い方をしてもらって新しいイノベーションを起こしてもらうことをすごく期待しているところです。
それぞれのまちの、それぞれの都市政策・交通政策を
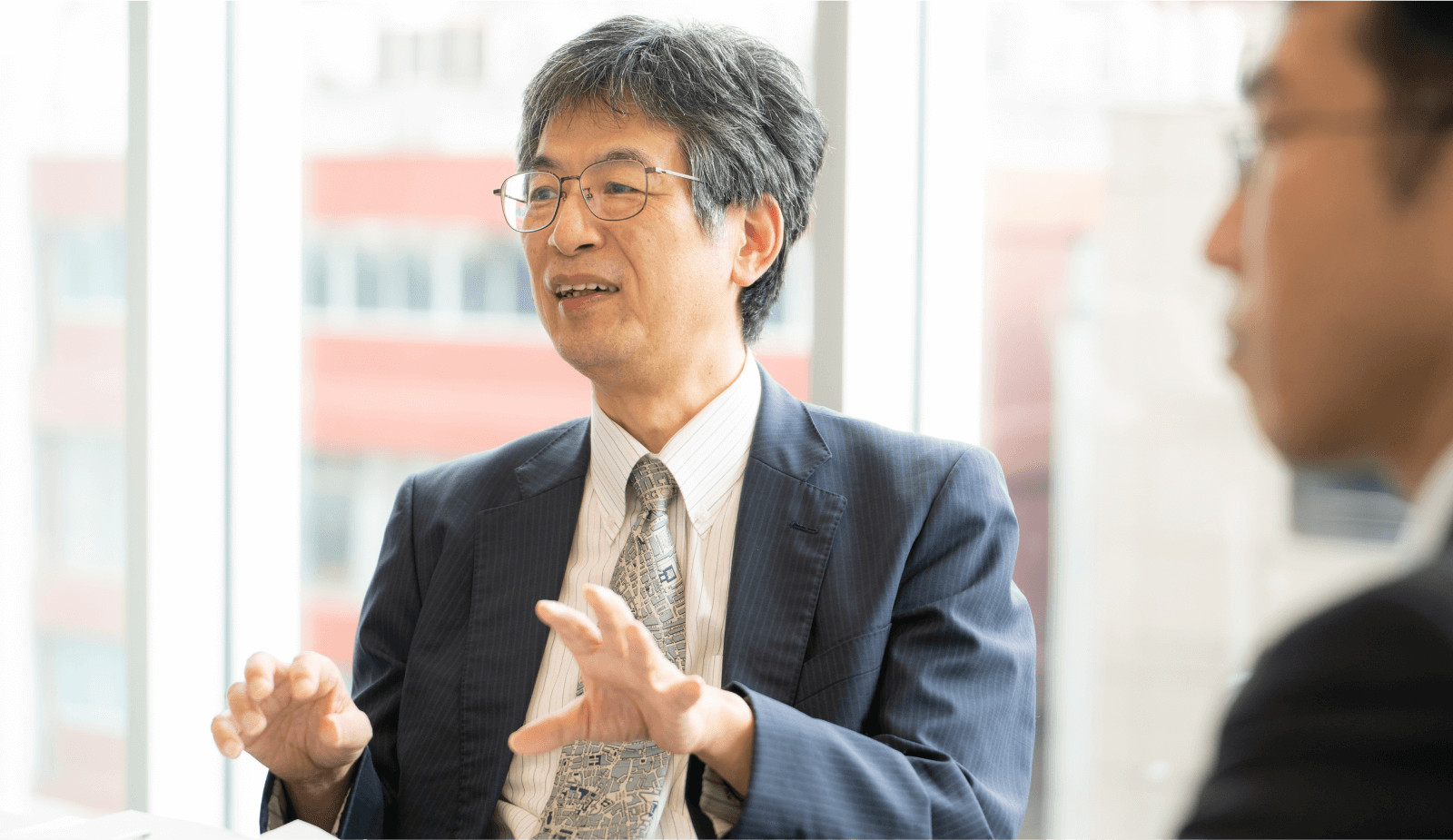
谷口先生:
これからのまちづくりに関しては、現在、国土交通省さんが想定されているような政策のメニューで着実に事例を増やして裾野を広げていくという感覚で良いかなと思っています。
「立地適正化計画」は、コンパクトなまちづくりを目指すものですが、政策を考える上でも人の動きはすごく大事で、それと連動して土地利用計画や交通計画に活かしていただけると良いのではないかというのが個人的な希望です。
田中室長:
おっしゃる通りで、「土地利用」と「移動」は結びつきが強いので、PT調査の立地適正化計画への活用というのは一番ぴったりな使い方なんだろうと思います。それから、ウォーカブルなまちづくりについても、「移動」と「滞留」は非常に大事な要素です。まちの中に人の流れや居場所をどうやって作っていくのかを考える際に、多様な活動がそこで行われることをイメージできるデータの使い方をしていただきたいと思います。
谷口先生:
PT調査のような質の高いデータと、ビッグデータなどを重ね合わせることで、行政の多様なニーズに応えられるという側面があると思うので、ぜひ、そういう使い方をしていただきたいですね。
田中室長:
現代は非常にスピードの速い時代です。課題を的確に捉え、施策を打つためにはデータを上手く使いこなすことが大事です。目に見えないことでも、データから分かることがあります。
一方、データに頼るだけでなく、現場に飛び込んで肌感覚をしっかり持っておくことも大事だと思っています。ちゃんとデータを取ってエビデンスをしっかりと持っておくことと、それが肌感覚と比べてどうなのか、担当者が理解した上で上手くデータを使っていただくことが大事だと思っています。
谷口先生:
「都市交通調査ガイダンス」は、好きなところだけを読んでくれるだけでも構いません。前から順番に読まなくてもいいんです。気になるところだけ読むというパターンでも全然かまわない。今回のガイダンスがなるべく多くの方々にとって身近なものになってくれれば幸いです。